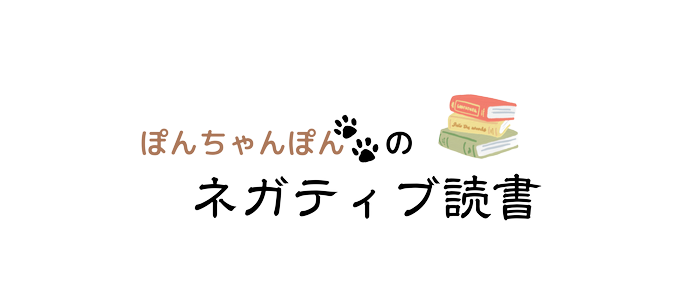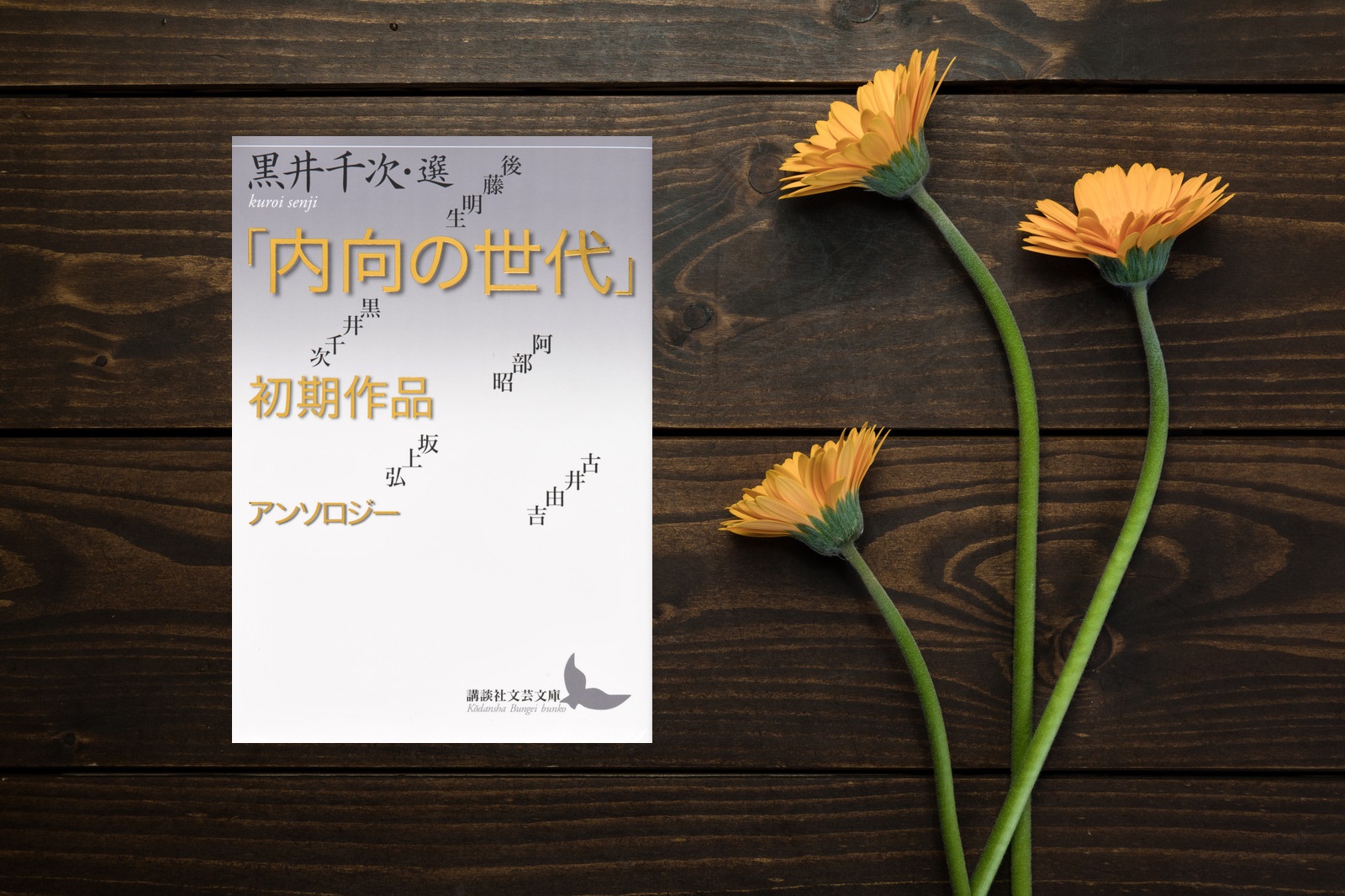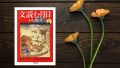この作品に触れたきっかけ
今回読んだ「円陣を組む女たち」は、本ブログではすでに数回取り上げた、「必読書150」の中にあった作品です。

私は上の必読書をすべて読むチャレンジ中なのですが、「必読書150」の中では現在は入手困難となっていましたが、講談社文芸文庫「「内向の世代」初期作品アンソロジー」黒井千次(選) の中に収録されているということを発見し、購入しました。
「内向の世代」とは?
恥ずかしながら、「内向の世代」という言葉を初めて聞いたため、参考まで解説を。
内向の世代(ないこうのせだい)とは、1930年代に生まれ、1965年から1974年にかけて抬頭した一連の作家を指す、日本文学史上の用語である。
Wikipediaより
1971年に文芸評論家の小田切秀雄が初めて用いたとされる。小田切は「60年代における学生運動の退潮や倦怠、嫌悪感から政治的イデオロギーから距離をおきはじめた(当時の)作家や評論家」と否定的な意味で使った。主に自らの実存や在り方を内省的に模索したとされる。
戦後に過激な政治思想活動があったなかで、それに対抗するように、自身の内部を突き詰めるような作品が書かれていたということなんですね。
「内向の世代」初期作品アンソロジー 収録作品
こちらはアンソロジーであり、「内向の世代」を代表する5人の作家の作品を、ほぼ同じ分量で掲載してあるとのこと。1作品が短めの場合は、2作品収録してバランスを取っているそうです。
【目次】
・まえがき(黒井千次)
・私的生活(後藤明夫)
・闇の船(黒井千次)
・鵠沼西海岸(阿部昭)
・日日の友(阿部昭)
・ある秋の出来事(坂上弘)
・円陣を組む女たち(古井由吉)
「円陣を組む女たち」作者・古井由吉さん 来歴
古井 由吉(ふるい・よしきち)
「「内向の世代」初期作品アンソロジー」、黒井千次(選)、講談社文芸文庫、講談社
一九三七・一一・一九~ 東京生まれ。東京大学大学院独文科修了。カフカ、ムージル、ヘルマン・ブロッホ等の翻訳・研究を行いながら金沢大学、立教大学の教員、助教授を経て、七〇年三月に退職。六九年「円陣を組む女たち」、七〇年「男たちの円居」「杳子」「妻隠」が芥川賞候補となり、「杳子」で受賞。『栖』で日本文学大賞、『槿』で谷崎潤一郎賞、「中山坂」で川端康成文学賞、『仮往生伝試文』で読売文学賞、『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞、その後、一切の文学賞を辞退。作品に『山躁賦』『白暗淵』『雨の裾』他がある。
残念ながら2020年2月18日に82歳で逝去されていました。
国語の教科書に作品が載っていたような気がしますが、具体的になんだったのか、思い出せませんでした…
円陣を組む女たち あらすじ
女たちは、あらゆる場面で円陣を組む―――
筆者が出会った、年齢も立場も時代も異なる女たち。
性の匂いを感じさせながら、時に男性に恐れを感じさせながら。
点で描かれるイメージが、語られるにつれ不思議とまとまりを見せ、ラストには筆者の幼少期の鮮烈な記憶と結びつく。女性とはなにか、という根本的な問いに対する回答を、繊細な描写で浮き彫りにする、古井由吉の初期短編。
※主のまとめであるため、もし異なる点ありましたらご容赦ください
本作品の特徴
特徴① 女性にまつわる様々なエピソード
読み始める前は、「円陣」を女性が組む場面というのはスポーツ以外にどんな場合なのか想像がつかず、一体どんな作品なのだろうと思っていました。
本作は、一つのできごとを長く話すのではなく、筆者の断片的な経験をつなぎ合わせた作品になります。そのため、作品中にはあらゆる「円陣を組む女性」が登場します。おおまかに書くと、下記のようなかたちです。
①春の公園でおしくらまんじゅう様の遊戯をしている15,6歳の少女たち(現在)
②夏のグラウンドで、ギリシア悲劇の練習をする学生たち(10年前)
③夕方の電車の中で見かけた、母親の仕立てた服を着た17,8の娘(現在)
④八百屋で商品を真剣に品定めする30過ぎの女性(現在)
⑤引っ越し先の分譲アパートから見た、向いの建物に住む女性の住民たち(現在)
⑥団地に引っ越した先輩の家を見に行った際に目にした、各階の住民たち(少し前の話)
⑦山登りの最中で出会った女学生2人(高校時代)
⑧学生運動をする男子学生と言い争いをする主婦(現在)
⑨その直後に出会った、学生運動をする女性(現在)
⑩最後の記憶(大事な部分なので詳細は避けます)
特徴② 時折差し込まれる性的なイメージ
本作を読んでいて気が付くのは、時折(というより、むしろ頻繁に?)差し込まれる性的なイメージです。それぞれのエピソードに登場する女性について、体つきについてであったり、その成長度合いについてであったり、著者が抱いた性的な感覚が正直に書かれています。
普通であればちょっと躊躇ってしまうところですが、著者にとって、それらの「異性」であるという感覚、自分とは違う気質を持った生物、という感覚は全体を通じて重要なものであったということなのでしょう。
特徴③ 女性への憧れと恐れ
②とも通じますが、女性に対する描写からは、著者の女性への憧れや恐れが読み取れます。
青年時代に出会った同年代の女性に対しては、青年らしい初々しさを感じさせますが、年上の女性に対しては醜悪さのようなものを感じるようになります。ですが、結局は若い女性に対しても、同様の“不快感”を感じるようになっていきます。
年の老若に関わらない“女の本質”のようなものが、男性である自分にとっては理解しがたいものであり、得体が知れないものである、という感覚が作品を通じて伝わってきます。
炙り出される女性の本質
「必読書150」の中で柄谷行人さんが「いつも微熱のなかで書かれている感じがする」と評したように、本作は現実と筆者の妄想に近いイメージが自由に行き来します。
ひとつひとつは断片的なエピソードながら、エピソードが語られるにつれ、それらはどこかで繋がっているという感覚を、読者は持つことになると思います。
最後にたどり着く、ある意味衝撃的なエピソードで読了すると、「女性の本質とはこういうものなのかもしれない」という、落としどころを得たような納得感がありました。
これを男性が書いたというのが驚きですし、ここまで感覚として女性をつかんで文章に起こすことが出来る筆力に感服。理論的な評論文ではこの感覚は得られないのでは、という不思議な感動がありました。わずか45ページほどの作品ですので、ぜひ読んでみていただきたいです。