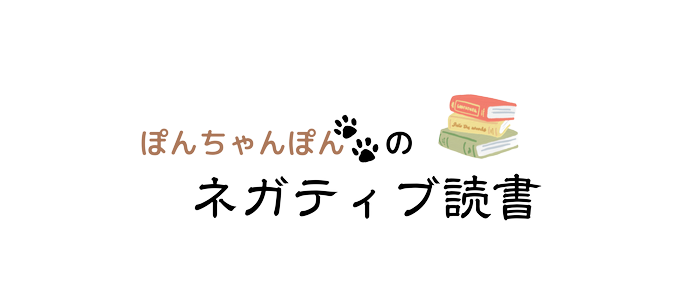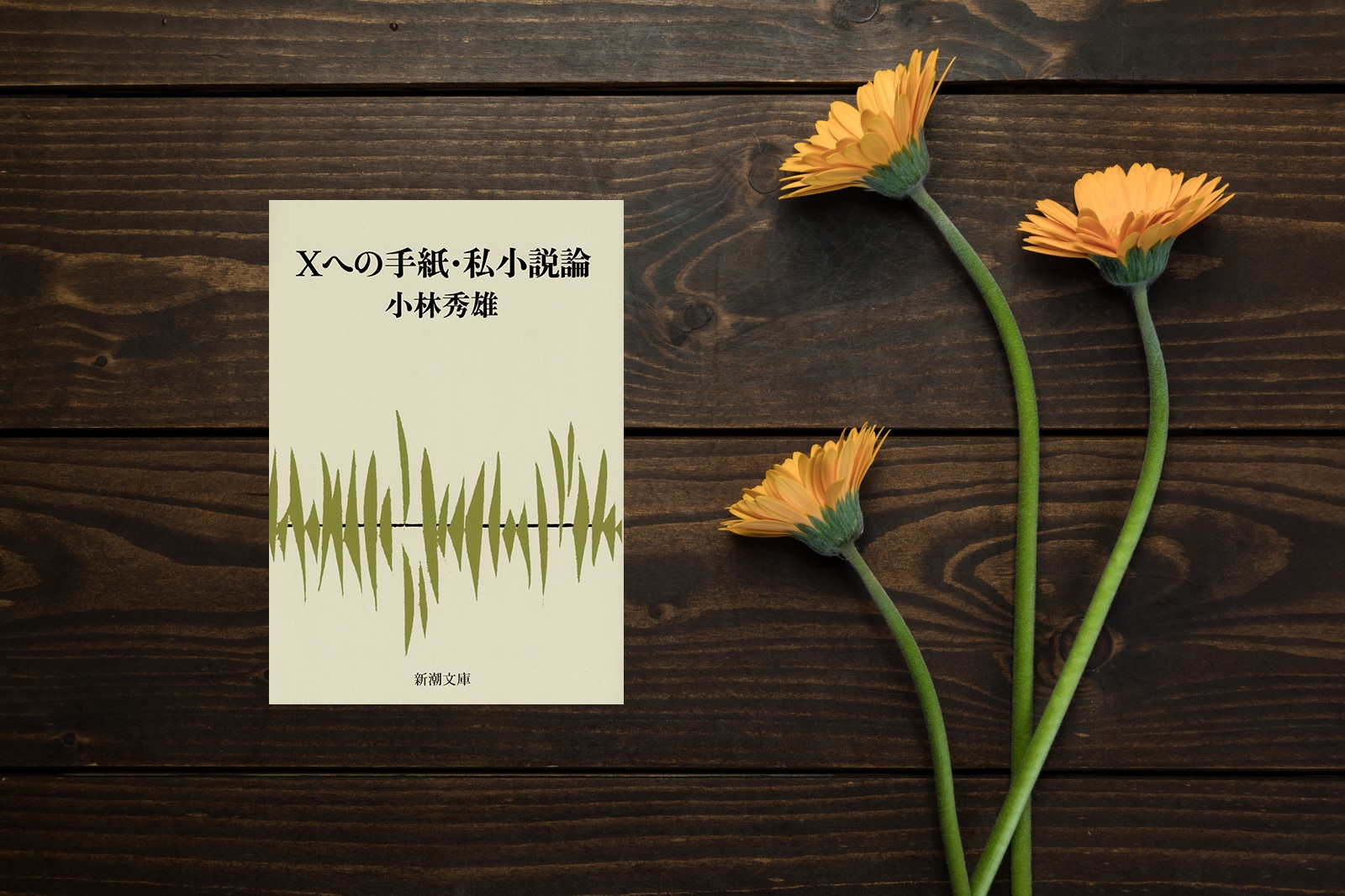こちらを読んだきっかけ
こちらについても、以前から何度かご紹介している「必読書150」に掲載されていたものです。
もともと小林先生は大好きでして、このブログでも1冊ご紹介しました。
そんな小林先生のデビュー作で、しかも必読書150に入っているのなら読むしかない!と思い、購入しました。「様々なる意匠」は、『Xへの手紙・私小説論』(小林秀雄、新潮文庫、新潮社)に収録されています。
小林秀雄(1902‐1983) 来歴
まず、著者 小林秀雄の来歴です。前回は中央公論新社でしたが、今回は新潮社版です。
東京生れ。東京帝大仏文科卒。1929(昭和4)年、「様々なる意匠」が「改造」誌の懸賞評論二席入選。以後、「アシルと亀の子」はじめ、独創的な批評活動に入り、『私小説論』『ドストエフスキイの生活』等を刊行。戦中は「無常という事」以下、古典に関する随想を手がけ、終戦の翌年「モオツアルト」を発表。’67年、文化勲章受章。連載11年に及ぶ晩年の大作『本居宣長』(’77年刊)で日本文学大賞受賞。2002(平成14)年から’05年にかけて、新字体新かなづかい、脚注付きの全集『小林秀雄全作品』(全28集、別巻4)が刊行された。
「Xへの手紙・私小説論」小林秀雄、新潮文庫、新潮社
やはりここにも書かれていませんが、小林は大学時代に、有名な詩人である中原中也と、女性を巡って三角関係になっており、最終的に自分がその女性と同棲していたということです。ちょっと意外ですよね。
様々なる意匠とはどんな作品なのか
「改造」誌とはどんな雑誌か?
そもそも「改造」という雑誌を見たことがないのですが、やはり1955年に廃刊となっていました。
ただ、1919(大正8)年の創刊以降、社会主義的な評論を多く掲載していた総合雑誌で、社会派の記事だけでなく、谷崎潤一郎や志賀直哉も連載するなど、文学的にも注目された雑誌であったようです。
この時の大賞は誰がとったのか?
なお、上にも書いたように、小林秀雄は大賞ではありません。次席でした。
では、大賞は誰がとったのか?答えは、当時東京帝国在学中であった(おまけに小林より年下)宮本顕治の「『敗北』の文学」です。私は恥ずかしながら存じ上げなかったのですが、この方も相当に大物で、日本共産党の指導的立場に長くおられたということです。
とはいえ、大賞作の「『敗北』の文学」は芥川龍之介について論じているという事ですので、おそらくそこまで政治色はなかったものと思われます。この評論もものすごく気になる!
にしても、この時の審査員の見抜く力、やばすぎです。
様々なる意匠 概要
この作品は懸賞応募作品ということですので、文庫にして約25ページと、短めの作品です。
内容は、批評家が引き合いに出しがちな“意匠”、ここではマルクス主義とモダニズムと私小説(写実主義)について批判しているということです。
しかし、この雑誌、社会主義的な雑誌なんじゃなかったんでしたっけ(^^; マルクス主義批判して大丈夫だったんかいな…まあ、賞とってるから、認められたんでしょうけど、随分と挑戦的な気がします。
様々なる意匠 感想
①ドヤ感がすごい
のっけから度肝を抜かれるのが、カッコつけた感じの、ドヤ感のすごい物言いです(ごめんなさい)。
さすがはデビュー作と言おうか。自意識が駄々洩れている。
第一、エピグラフ(小説の最初についている、他の人の言葉や詩の引用です)ついてるんですよ。懸賞作品ですよ?まだ素人である段階で、いかにもいっちょ前みたいにしている。しかも引いてるのがアンドレ・ジイドってところがまた…いや、でもそういうところ、嫌いじゃないです笑。
参考まで、冒頭部分を。
吾々にとって幸福なことか不幸な事か知らないが、世に一つとして簡単に片付く問題はない。遠い昔、人間が意識と共に与えられた言葉という吾々の思索の唯一の武器は、依然として昔乍らの魔術を止めない。
「Xへの手紙・私小説論」小林秀雄、新潮文庫、新潮社、P113
なんとなく伝わりますでしょうか。「魔術」ってワードを普通に使っているところがすごい。
②小林の批評に対する姿勢が垣間見える記述
私は、この作品を読んで、これから自分はこういう姿勢で批評をやっていくんだ、という決意表明のように感じました。
小林秀雄の批評は、理論的な記述というよりは感覚的、感情的な感じがしますが、読む側を興奮の渦に巻き込む力がすごいのです。小林自身、自身の感動や情熱を伝えることが大事だと考えていたのではないかな、と「様々なる意匠」を読んで感じました。
たとえば、次のような箇所です。
だが、批評の方法が如何に精密に点検されようが、その批評が人を動かすか動かさないかという問題とは何んの関係もないという事である。
「Xへの手紙・私小説論」小林秀雄、新潮文庫、新潮社、P115
人間を現実への情熱に導かないあらゆる表象の建築は便覧に過ぎない。
「Xへの手紙・私小説論」小林秀雄、新潮文庫、新潮社、P121
実際、小林の批評は感情的に過ぎるという批判がありますが、それをすでに見越していたかのような書きぶりで、凄みを感じました。
③「様々なる意匠」で小林秀雄は何が言いたかったのか?
では、小林はこの作品を通じて何が言いたかったのか。
色々と回りくどい感じもしましたが、私としては、「流行りの形式にとらわれることなく、人を感動させる作品を作ることにこだわれ!」ということなのかな、と思いました。
この作品の中で「意匠」というのは上にも書いたようにマルクス主義、モダニズム、私小説と、当時もてはやされた形式や主義を指しますが、それらはあくまでその時の流行りに過ぎず、人の心をつかむには、これらの根底にある「心」のようなものをきちんと捉えなければならないということ、形式を模倣しても意味がない、ということが言いたかったのではないかと思いました。
正直、ところどころ何を言ってるのかよくワカラナイ部分もありましたが、小林秀雄は一言一句精読して理解しようとすると迷宮入りしますので、全体をつかんでから逆読みしていった方がスッと入る気がしていますし、上の考えが根底にあると思いながら読むと、比較的スムーズに内容が理解できた気がしました。
小林秀雄は読めば読むほど興味が湧く作家です。これからも継続して読み続けたいと思います。