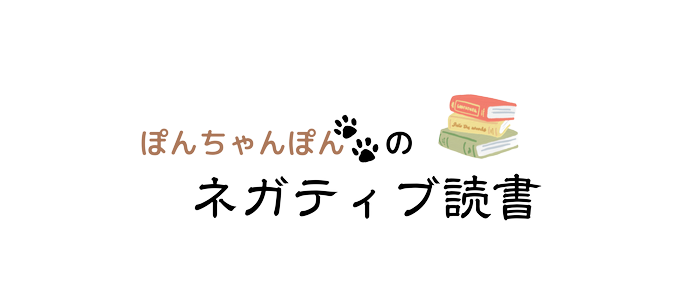この本を読んだきっかけ
有隣堂さんは、神奈川県在住の私にとっては、とても馴染み深い書店でした。
さらに就職後は仕事上でも関わることがあり、ますます身近に感じていた存在でもありました。
今でもよく書店に足を運んでいるのですが、そこに貼ってある「YouTubeやってます。」のポスターと、なにやら不気味なぬいぐるみの写真も目には入っていましたが、チャンネルを観るには至っていませんでした。
では、何きっかけで観たかと言いますと、確か、一時期小説家を目指していた時期があり、作家さん関連のYouTubeをあさっていたところ、中村七里先生を特集している回がヒットし、そこからハマったと記憶しています。とにかくMCのR.B.ブッコローの中の人が秀逸なんです。
そのゆうせかから本が出ているということで、応援の意味もこめて購入しました。
あらすじ
神奈川県を中心に展開する創業明治42(1909)年の老舗書店「有隣堂」。
そんな有隣堂の公式企業YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」が待望の書籍化!「有隣堂しか知らない様々な世界を、スタッフが愛を込めてお伝えする」をコンセプトにした同チャンネルは、有隣堂社員や社外ゲストによる熱のこもった商品のプレゼンと、MCであるR.B.ブッコローの「正直すぎる」感想が評判となり、開設約2年半で登録者数20万人を超える人気チャンネルに成長。
チャンネル名は「ゆうせか」、ファンは「ゆーりんちー」という愛称で親しまれています。「書店なのに本を売る気がなくて心配」
「老舗書店「有隣堂」が作る企業YouTubeの世界 ~「チャンネル登録」すら知らなかった社員が登録者数20万人に育てるまで~」
「MCキャラクターが正直すぎて面白い」
「出てくる社員のクセが強すぎる」
などと評されることの多い人気チャンネルはどのようにして生まれたのか?
本書は、その裏側について制作チーム自らが語るビジネス書です。
有隣堂YouTubeチーム、ホーム社
この作品のよいところ
ここでは、「YouTubeチャンネル」のよいところではなく、あくまで「本」のよいところとして書きます。
①カラーページもありの読みやすさ
YouTubeチャンネルの紹介本ということもあり、内容には写真もふんだんに盛り込まれていますし、字も大きめで、非常に読みやすいです。
最初の部分はオールカラーでMCであるR.B.ブッコロー(ミミズク)の紹介や、登場する社員さんの紹介ページもあり、チャンネルを観たことのない人にもよく内容が伝わる内容になっています。
②社員を大事にしている姿勢が伺える、豊富に盛り込まれた社員・スタッフへのインタビュー
このYouTubeでは多くの有隣堂や有隣堂運営店のスタッフさんが登場するのですが、みなさんキャラが濃いというか、いい味出してます。編集もあるとは思いますが、皆さんとっても楽しそうに撮影されているようなので、観ている方も楽しくなります。
この本では、主に登場する社員さんの単独インタビューがいくつか収録されているのですが、その楽しい雰囲気が文面から伝わってきます。会社そのものをアピールするというより、社員のよさを引き出してアピールしようという姿勢が、会社が社員を大事にしている感じがして、良いなと思います。
③とにかく正直に語っているところ
私がこの本を読んで驚いたのは、今の形になる前に一度うまくいかない時期があったということ。
てっきり今のかたちでスタートしたものと思っていたのですが、一度挫折があったということです。一度始めたものをリセットして、何が悪かったのか分析し、再スタートさせるというのは、すでに表に出してしまっている以上相当ハードルが高い事だったと思います。
次は失敗できないというプレッシャーのなかで、外部プロデューサー(この方の功績はすごいと思います)を入れ、新キャラを作るという大ナタを振るった結果、登録者数20万人越えという結果につながりました。
読んでいて感じたのは、「正しい誠実な努力は実を結ぶ」ということです。正しく悩んで、正しく努力し、正しい決断をすれば、ちゃんと結果になって返ってくる。そんな当たり前といえば当たり前のことかもしれませんが、実録として示されていることが勇気をくれます。
これからも応援します!
地元の書店が、紙の本が売れなくなるなかで、これまでの流れを打ち破って新しいことをしようと試行錯誤している様は、なんだか嬉しくなりましたし、励まされました。
神奈川県に住んでいなくて、有隣堂自体を知らない人であっても、sakusaku(昔テレビ神奈川で放映していた音楽番組。ブッコローに似たキャラが活躍していた)を知らない人であっても、十分楽しめる内容ですのでぜひ読んでほしいです(もちろんYouTubeも)。
この本についても、なにか一つの仕事をするなかで大事なことがギュッと詰まった内容になっていると思いますので、気楽に楽しく読めるビジネス本としておすすめです!