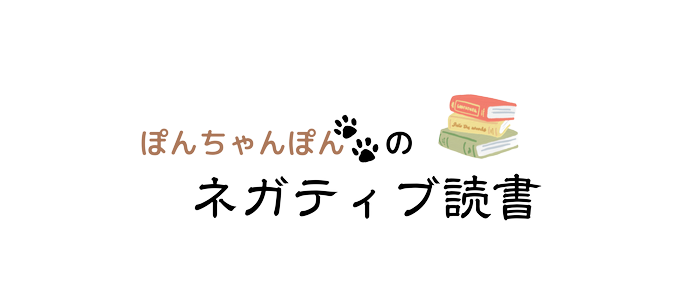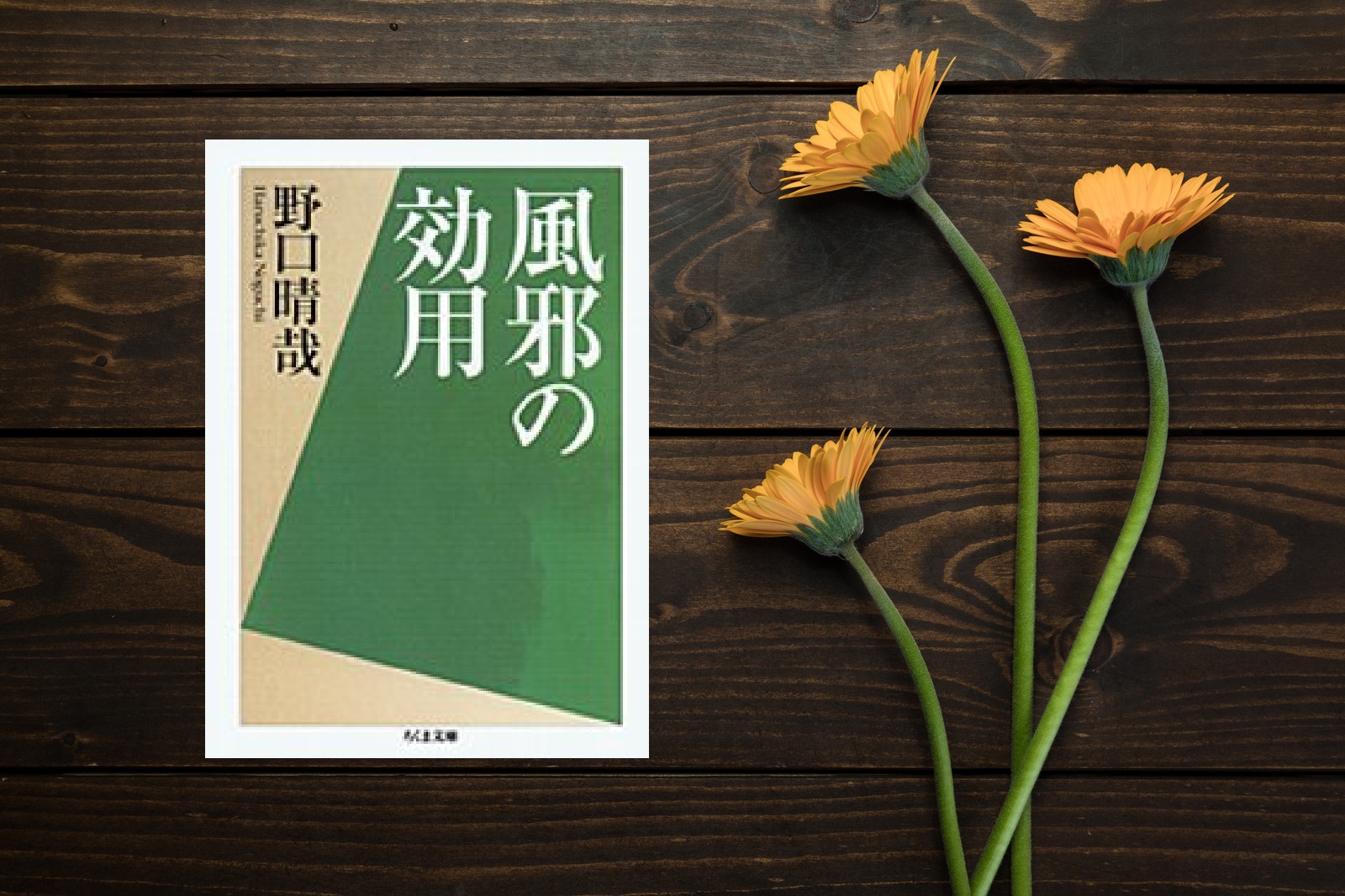この本を読んだきっかけ
この本、よくちくま文庫フェアなどで見かけていて、平積みにもなっているので、以前から気になっていました。雑誌のおすすめ本特集などでも時々見かけていました。
実は私も病気に身を任せるところがあり、風邪を引いた後は、それまでのダルさが取れて風邪を引く前より元気になれる気がしており、共感できそうだと思い、購入しました。
概要
風邪は自然の健康法である。風邪は治すべきものではない、経過するものであると主張する著者は、自然な経過を乱しさえしなければ、風邪をひいた後は、あたかも蛇が脱皮するように新鮮な体になると説く。本書は、「闘病」という言葉に象徴される現代の病気に対する考え方を一変させる。風邪を通して、人間の心や生き方を見つめた野口晴哉の名著。
「風邪の効用」野口晴哉、ちくま文庫、筑摩書房
ちくま文庫では「整体入門」という、整体を中心とした著書もあり、セットで読むとよいと帯にありました。
著者 野口晴哉(のぐち はるちか) 来歴
「社団法人整体協会」創設者。1911(明治44)年東京生まれ。17歳で「自然健康保持会」を設立。整体操法制定委員会を設立し、療術界で中心的役割を果たす。しかし治療を捨て、1956(昭和31)年文部省体育局より認可を受け「社団法人整体協会」を設立し、整体法に立脚した体育的教育活動に専念する。1976(昭和51)年没。主な著書に本書のほか、『整体入門』(ちくま文庫)、『体癖1、2』『育児の本』『躾の時期』(株式会社全生社発行)等がある。
「風邪の効用」野口晴哉、ちくま文庫、筑摩書房
17歳で団体を立ち上げ!!半端ないです。
野口さんの理論は非常に特殊です。民間療法に近いというか、気を送る治療を行うなど、少し「?」なものもありますが、「人間本来の自然の治癒力を高める」という考えに基づいた治療哲学は、学ぶところがとても多いものとなっています。
印象的な考え方
印象的な考え方① 風邪は病気というよりも治療行為
タイトルにも「風邪の効用」とありますように、野口さんは風邪はただの病気ではなく、溜まった不調の発露と考え、きちんと風邪を引き、きちんと治すことによって体が整うと言います。
また、急いで治してしまおうとすると、根本的な解決にならずに、風邪を繰り返してしまう、とも。一度風邪になったら、薬で無理やり抑え込むのではなく、安静にして「きちんと」症状に向き合って治すということが体にとって必要だといいます。
忙しい現代人は、仕事を休むこともままならないので、とにかく症状を早く抑え込みたい、という気持ちになってしまいがちです。ですが、病気になるという事はある意味「毒出し」の儀式のようなものだと私は思いますので、そう考えれば、確かに風邪そのものがある意味「治療行為」とも言えそうです。
印象的な考え方② 整体は患者自身で行うことが大事
これは現代人はハッとさせられる言葉なのではないかと思います。
私たちは普段具合が悪くなれば、とにかくまず市販薬、無理なら病院で、医者の診断に黙って従い、もらった薬を黙って飲んで治るのを待ちます。
ですが、野口さんは、風邪というのは人それぞれで原因となっている箇所が異なるため、それを自身で観察することが必要、と言います。人にはそれぞれ体の動かし方のクセがあり、それによって硬くなった部分から風邪になる、というのです。
もちろん腕のいい医者であれば個々の体のクセをすぐ見抜けるのかもしれませんが、普通の医者であればそこまでひとりひとりを丁寧に診る時間はないわけで、出ている症状に対して定型化された処方をすることになります。
それでもいずれは治りはするでしょうが、それだけで終わりにするのではなく、自分の体をしっかり向きあい、「なぜ自分は風邪になったのか」ということを考えることで、長期的に健康でいられるためのヒントを得られるといいます。
人に治してもらうということに慣れきっている現代人にとって、これは非常に大事な視点であると思います。
印象的な考え方③ 心と体はつながっている
ここが野口さんの健康法のユニークなところなのですが、心の動きが体にもたらす効果も自然に考慮に入れているということです。
非常に面白いと思ったのは、次の部分。
「あの人は自分を見てくれない、病気になれば親切にしてくれるだろう」と思うと病気になりたい要求が起こる。(中略)そういう心で風邪を引いたのだから、「私が風邪を引いたというのにちっとも親切にしてくれない」とか、「こんなことで治ったら損だ」などという考えも出てくるわけです。
「風邪の効用」野口晴哉、ちくま文庫、筑摩書房、p99
心配してほしくて病気になりたくなること、確かにありますよね。
野口さんは、その気持ちで本当に風邪になってしまう、と言います。また、風邪を引いたと思いこむと、本当になってしまう、とも。
西洋医学の影響なのか、私たちはとかく病気というと、症状や、検査の数値などから病気を特定して手術や薬の処方を受けるというのが基本で、心理的要因というのは切り離して考えがちです。
心の動きがどのように体に影響しているかというのは数値で測れませんし、関連付けも非常に難しいようので、通常は上記の対応でよいと思いますが、心の問題が体まで悪くしてしまうことがある、というのはみなさんも直観的に理解していると思います。心と体はつながっている、という視点は時々気に留める必要があると、改めて考えさせられました。
アフターコロナのいま、風邪を引くことの大切さを考える
ここのところ、数年続いたコロナ禍もようやくひと段落してきました。
ですが、ここ数年、コロナ対策に神経を尖らせつづけてきたせいで、コロナ以外で風邪様の症状が出ることが極端に少なかったのではないでしょうか。
病気にあまりならなかったことは喜ばしいことですが、個人的には、体の溜まった疲労を放出する機会を失い続けた時期でもあったと思っており、長期的に見た健康という意味では相当に体に負担があった時期であったと思います。
これからもしばらくは、熱が出るたびにコロナの不安を感じることにはなるでしょうが、必要な風邪は引くべきものであるし、まったく風邪を引かないことはむしろ危険であるということをこの本は思い出させてくれます。
健康の在り方を見直すのに、今非常に示唆に富んだ本だと思います。おすすめです!