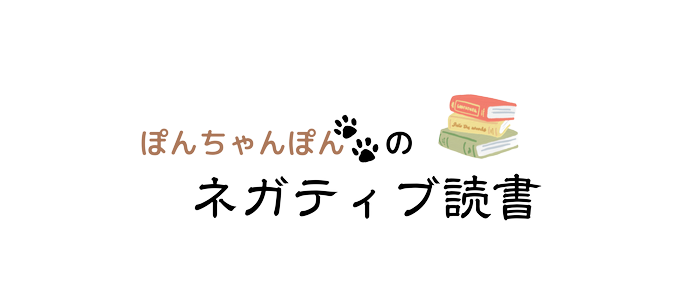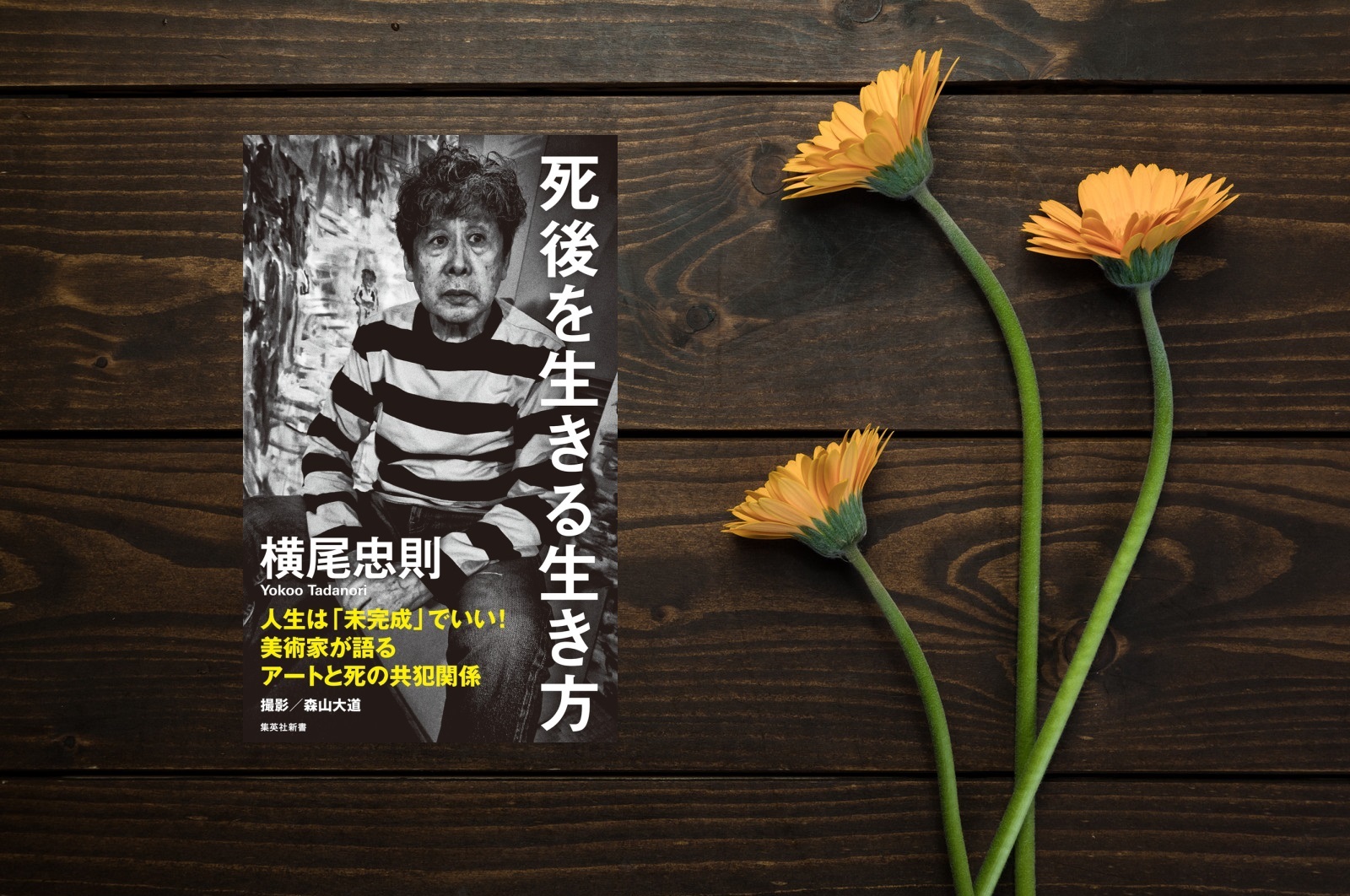こちらを読んだきっかけ
横尾忠則先生はここ数年ずっと気になっている存在で、先生の絵を家に飾っています。
最近「横尾忠則 寒山拾得展」もやっていたということで、こちらも気になっていたところ、丁度NHKで特集番組があり、展覧会を見に行くと決めたのとほぼ同時に、こちらが新刊で出ている事を知り、展覧会の内容ともリンクしているようだったので、購入!(展覧会も後日見に行きました!よかった!(展覧会は2023年12月3日で終了))
概要
人は死んだらどこへ行く? そんな夢想は結局、「死=無」という地平線上におさまったりする。だが、死の世界はそんな凡庸なものではない――。87歳を迎えた世界的美術家が、死とアートの関係と魂の充足について自由闊達につづる。父母、愛猫の死から三島由紀夫、アンディ・ウォーホルらとの交流の記憶まで。貴重なエピソードを交え、「死」とは何か? 「死後を生きる」とはどういう境地なのかを考えていく。「人間は未完で生まれて、完成を目指して、結局は未完のままで死ぬ。これでいいのです」その言葉に触れればふっと心が軽くなる、横尾流人生美学。
横尾忠則「死後を生きる生き方」集英社新書、集英社
著者 横尾忠則さん 来歴
1936年兵庫県出身。美術家。1972年、ニューヨーク近代美術館で個展。その後も各国のビエンナーレに出品、パリのカルティエ財団現代美術館、東京国立博物館他、内外で個展を開催。国際的に高評価を得る。毎日芸術賞、紫綬褒章、旭日小綬章、朝日賞、高松宮殿下記念世界文化賞等受賞多数。令和2年度東京都名誉都民、2023年日本芸術院会員に。著書に小説『ぶるうらんど』(泉鏡花文学賞、文藝春秋)、『言葉を離れる』(講談社エッセイ賞、青土社)、小説『原郷の森』(文藝春秋)他多数。
横尾忠則「死後を生きる生き方」集英社新書、集英社
感想
感想①思った以上にオカルト
のっけから驚かさせられるのは、今日ではあまり言われなくなったようなオカルト感のあるお話しが満載であるというところ。
輪廻転生というものがあると先生は考えていて、ひいては霊もあるというのが一貫した論です。先生に言わせれば、死んだら無になり、また生まれたらみんな0からのスタートとする方がむしろ不自然だというわけです。
人間が転生しないという考えは実に不自然です。もし、転生がなければ、すべての人間が平等であるということになります。この社会で、人間が不平等であるということ自体が、輪廻を肯定する証拠です。
横尾忠則「死後を生きる生き方」集英社新書、集英社、p77
普通の人がこんなことを言うと「ヤベー奴」と思われてしまいそうですが、先生が言うと「そうなのかも…」と思ってしまいます。
感想②オカルトとの向き合い方について
現代は科学的なので、こういったあの世とか、霊とか、輪廻転生とかは否定されがちですが、果たして絶対にないと言えるのか。何も考えずに頭ごなしに否定するのではなく、ちょっと立ち止まって考える姿勢が必要な気がします。
私が驚いたのは、次の箇所。
僕が以前、フランスに行ったとき、…中略…ある日、科学者と哲学者と宗教学者との会合へ連れていかれたんです。…中略…そのときに、そういう人たちに交じって、霊能者や錬金術師や占い師のような人がいっぱい来ていたんです。おばちゃんたちなんですけれど、どうみても魔女なんです。そういう魔女のような人たちと科学者、哲学者、宗教家が一緒になって、さまざまなテーマについて話し合う。そういう場だったんです。そんなのは日本にはないですものね。…中略…あれを見た途端に、うわぁ、日本は百年遅れている、ダメだな、てんで敵いっこないと思いました。
横尾忠則「死後を生きる生き方」集英社新書、集英社、p91~92
世界にはこういう場所もあるのかと、感心してしまいました。
オカルトをオカルトと断罪して切り捨てるのではなく、お互いの立場を尊重して語る文化。素晴らしいですね。どちらか一辺倒になるのではなく、この分野は科学的に、この分野は超常現象もあり得るかも、と、両方の視点から物事を見ることができれば、もう少し柔軟でバランスの取れた考えができるのかもしれません。
感想③さすがの独特な思考。でも不思議な説得力
先生の絵を見ていると感じるのが、「本当にこの方は芸術家なんだな」と。当たり前ですが(笑)。とことん感性でやっているというか…理屈ではなく、感覚でやってのけてしまう。見ている側も、先生の書いた絵を見ると「なんかすごい」という感覚になる。これはすごいことです。
この本に書いてあることは、現代日本ではなかなか大きな声で言いづらい、非科学的な内容が多く含まれていますが、この人が言ってくれたことで「そういう発想もあっていいんだな」と安心できます。そういう役割を担える日本人が、果たして今の日本に何人いるでしょうか。
科学に走り過ぎる世の中に、先生はこのように警鐘を鳴らしています。
AIによって、勝つ、負けるといったことが一層際立ってくれば、人間はどんどんどんどん、霊性、霊格から外れていって、野蛮な存在になっていくかもわからないですね。
横尾忠則「死後を生きる生き方」集英社新書、集英社、p145~146
AIをはじめとする科学技術の進歩によって、人間は魂、霊性、霊格といったものから、これからますます離れていくと思います。離れていくだけでなく、すごく大事なことを喪失していっているんだと感じます。
この本にも色々な本が登場していたので、関連して読んでみたいと思いました。特にダンテの「神曲」、横尾先生の小説「原郷の森」は非常に気になりました。