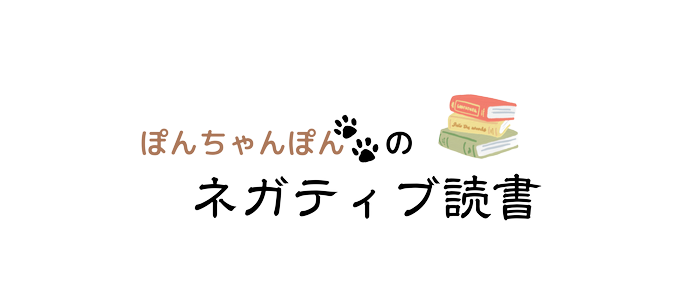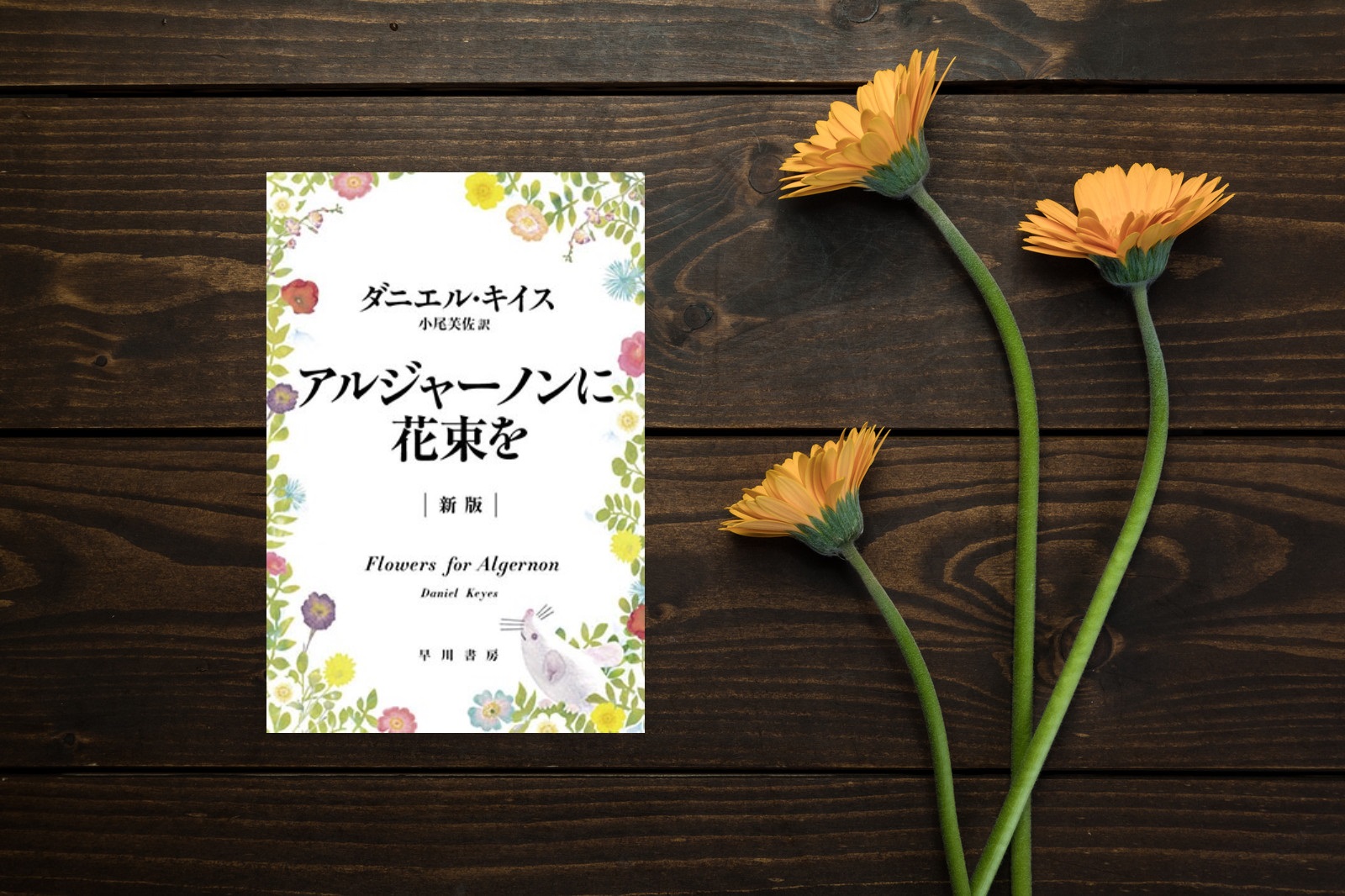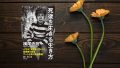この本を読んだきっかけ
この本は超有名ですよね。これまで幾度となく雑誌の本特集などで目にしてきました。ですが、天邪鬼な私は感動作、感動作と言われると読む気が失せてしまうため、どうしても手が伸びませんでした(笑)。
ところがふと「そろそろ読んでみようか…」という心境になったためチャレンジ!
あらすじ
32歳になっても幼児なみの知能しかないチャーリイ・ゴードン。そんな彼に夢のような話が舞いこんだ。大学の先生が頭をよくしてくれるというのだ。これにとびついた彼は、白ネズミのアルジャーノンを競争相手に検査を受ける。やがて手術によりチャーリイの知能は向上していく…天才に変貌した青年が愛や憎しみ、喜びや孤独を通して知る人の心の真実とは? 全世界が涙した不朽の名作。著者追悼の訳者あとがきを付した新版。
ダニエル・キイス「アルジャーノンに花束を」ハヤカワ文庫、早川書房
アルジャーノンは主人公の名前ではありません。ネズミの名前だったんですね~
では、タイトルの「アルジャーノンに花束を」とはどういう意味なのか?最後にタイトルの意味がわかると、まぁ泣けます。
著者ダニエル・キイス 来歴
1927年ニューヨーク生まれ。ブルックリン・カレッジで心理学を学んだ後、雑誌編集などの仕事を経てハイスクールの英語教師となる。このころから小説を書きはじめ、1959年に発表した中篇「アルジャーノンに花束を」でヒューゴー賞を受賞。これを長編化した本書がネビュラ賞を受賞し、世界的ベストセラーとなった。その後、オハイオ大学で英語学と創作を教えるかたわら執筆活動を続け、『五番目のサリー』『24人のビリー・ミリガン』(以上、早川書房刊)など話題作を次々と発表した。2014年6月没。享年86。
ダニエル・キイス「アルジャーノンに花束を」ハヤカワ文庫、早川書房
本作でも心理学者が重要な役割を果たしますが、筆者自身も心理学の知識があってのことのようですね。
感想
感想①訳者大変だこりゃ
内容と直接関係ない話ですが、読み始めてまず最初に感じたのは訳のこと。
この話は主人公のチャーリイ自身の手による報告書がベースとなって進みます。よって、チャーリイの知能の発達に伴い、文面もどんどん変わります。最初はひらがなかつ誤字だらけですが、真ん中あたりにくると漢字ぎっしりで、濃度が全く違います。
読んでいる側とすればわかりやすいですが、元はといえばこの作品は英語。英語でのたどたどしさを日本語に置き換える、しかも、もとの世界観は変えず…というのは生半可な苦労ではなかったと思います。実際、ダニエル・キイスさんもどう訳されているか大変気にしていたそうですが、訳者の小尾さんは悩んだ末、知的障害のある天才画家山下清さんの文章を参考にすることを思いついたそう(訳者あとがきより)。訳者さまさまであります。そのお陰で我々はこの本に触れることができるわけで、ありがとうございます!という気持ちになります。
感想②賢ければいいということではない…のか?
チャーリイは知能が発達するにつれ、世の中の真実を突きつけられることになります。
仲間だと思っていた人たちが、実は自分を馬鹿にし、不正の片棒を担がされていたこと。尊敬していた自分を治療してくれた博士たちへの失望。離れていた家族との悲しすぎる再会。知能がそのままであれば一生知らずに済んだであろう心の傷を、チャーリイは次々と感じてしまうことになります。
私はこの本を読んでいて絶えず脳裏に浮かんでいたのは、「満足な豚よりも不満足なソクラテスでありたい」という言葉です。チャーリィは急速に知能が発達したことによってたくさん苦しみましたが、それらは人間としてとても大事な経験であったと思います。
感想③知的障害者に対する健常者の態度について学ぶ点が多い
この本を読んでいて強く感じたのは、健常者の知的障害者に対する態度がいかに本人を傷つける可能性があるかということ。もちろん筆者も読者も健常者であるため、あくまで想像ではありますが、筆者のダニエル・キイスさんは教師時代に知的障害児と接する機会があったということで、ある程度説得力があると思います。
チャーリイが心に傷を負っていた原因は、知能が低いということよりも、母親がやっきになってチャーリイを通常の知能にしようとした挙句、それができない不満をチャーリイにぶつけ、そのうえ健常者の妹と比較し、チャーリイにつらくあたるようになったこと。周囲の態度が深い傷を負わせていたのです。
さらに、チャーリイは治療により知能が発達し、学会に被験者として参加したとき、自分がいかに元々知能が低く人間とみなされていなかったかをまざまざと見せつけられることになります。それは、知能が低い時も人間であった、という自身の認識と大きく異なるもので、知能の低い状態は人間ではないと言われているような発言に強くショックを受けます。
知能が低いことが悲劇なのではなく、周囲の態度が悲劇を産んでいるのかもしれない、ということに意識を持つ必要があると思いました。
感想④チャーリイが発見した人生の真実とは
自身への治療を行った心理学の教授に対してチャーリイが語ったことが、非常に印象的でした。
「知能は人間に与えられた最高の資質のひとつですよ。しかし知識を求める心が、愛情を求める心を排除してしまうことがあまりにも多いんです。これはごく最近ぼくがひとりで発見したんですがね。これをひとつの仮説として示しましょう。すなわち、愛情を与えたり受け入れたりする能力がなければ、知能というものは精神的道徳的な崩壊をもたらし、神経症ないしは精神病すらひきおこすものである。つまりですねえ、自己中心的な目的でそれ自体に吸収されて、それ自体に関与するだけの心、人間関係の排除へと向かう心というものは、暴力と苦痛にしかつながらないということ。」
ダニエル・キイス「アルジャーノンに花束を」ハヤカワ文庫、早川書房、p364
難解ですが、私なりに解釈すると、知能が高い事、仕事ができること至上主義みたいになってしまうと、暴力的な方向に向かうと。最近能力主義が万延しているような気がしていて、頭がよければ人を小馬鹿にしたような態度を取ってもよい、というような風潮があるような気がしていますが、それではよくないよ、ということなのかなと思いました。
知的障害から天才へ、すべての知能の立場を経験したチャーリイの生き方や態度、言葉から、あなたは何を受け取るでしょうか。納得の名作です。