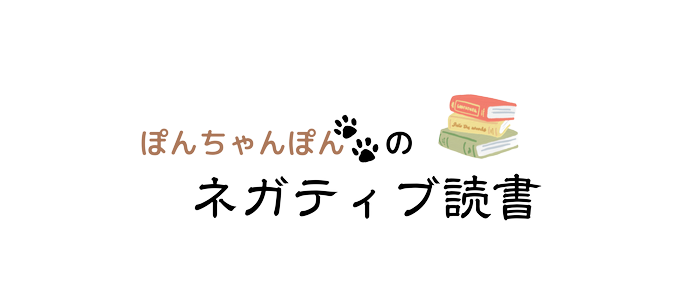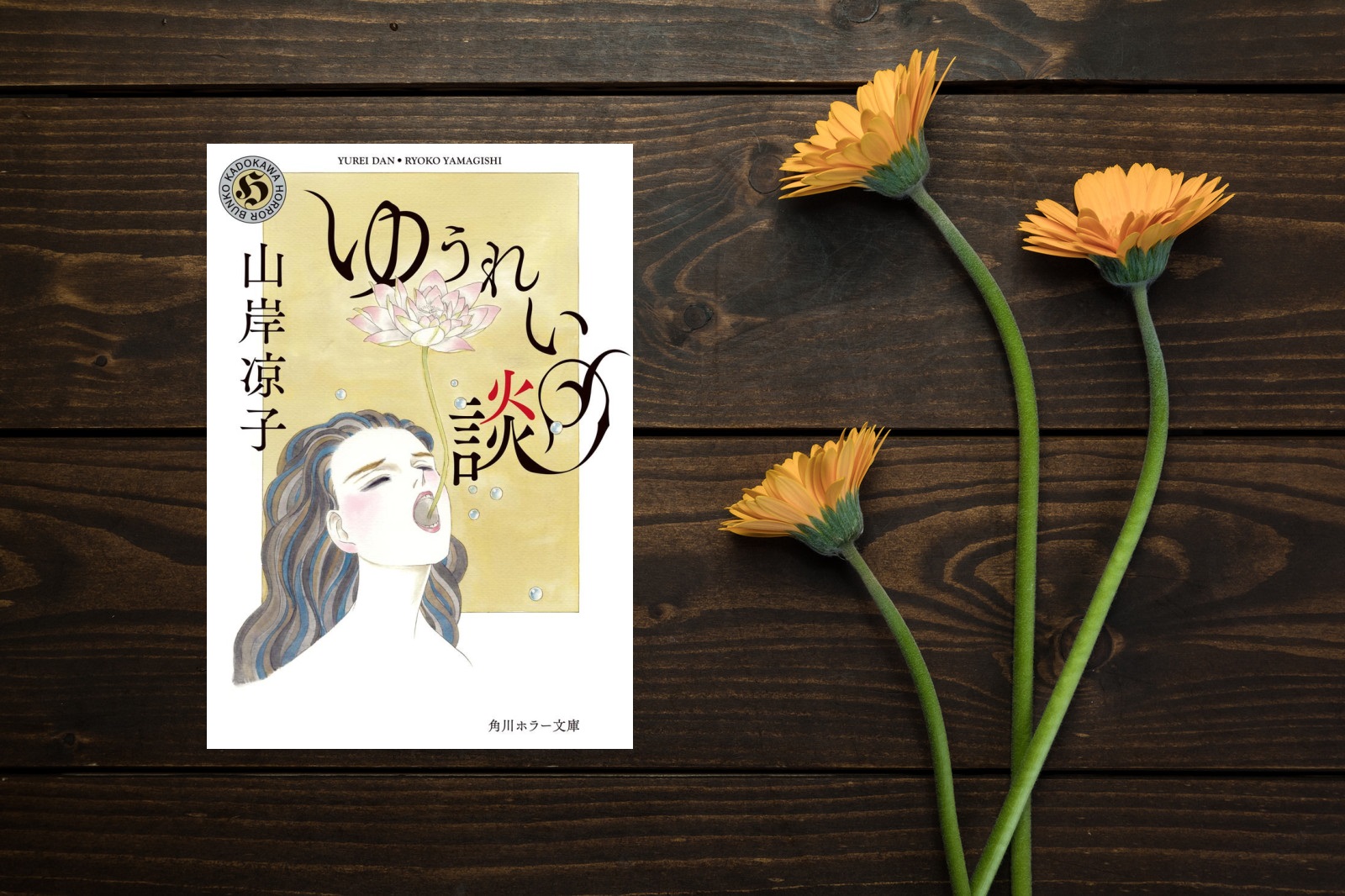この本を読んだきっかけ
私は何を隠そうマンガ、特に昔の少女マンガ大好き勢であります。これは母親の影響です。母親の薦めるマンガばかり読んでいたため、私の好きな漫画家はその時代の人ばかり笑。
特に山岸凉子先生は大大大好きで、かなり読みこんできていますが、最近角川ホラー文庫で短編集などが出されており、今回この「ゆうれい談」は未読だったため、購入した次第です。
山岸先生は霊感があるというのは有名な話で、だからこそ先生の書かれるホラーは怖過ぎて、今まで読むことができなかったのです。ただ、今回の話はすべて実体験ということで、怖がらせる方向に全振りしていないようだったので、これならいけるかな、と思いました。
山岸 凉子さん 略歴
1947年北海道生まれ。69年『りぼんコミック』5月号に掲載された「レフトアンドライト」でデビュー。71年『りぼん』10月号より連載が開始されたバレエ漫画『アラベスク』の大ヒットにより人気マンガ家となる。83年『日出処の天子』で講談社漫画賞少女部門を、2007年『舞姫 テレプシコーラ』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。ほか『白眼子』『レベレーション(啓示)』など多数。最新刊に『艮(うしとら)』がある。
山岸凉子「ゆうれい談」角川ホラー文庫、KADOKAWA
概要
漫画家にとって最大の敵は睡魔。山岸プロでの眠気ざましの話題は“ゆうれい談”。萩尾望都、大島弓子など著名漫画家たちの不思議体験談を始め、アシスタントさんが経験した怪異譚、著者が旅先や自宅で遭遇したほんとうにあった怖い話や魔訶不思議な話を満載。怖いけれど怪異を蒐集せずにはいられない著者のゆうれい談。表題作ほか、「読者からのゆうれい談」「蓮の糸」「ゆうれいタクシー」「タイムスリップ」 の5作を収録。解説:小野不由美
山岸凉子「ゆうれい談」角川ホラー文庫、KADOKAWA
あの「綿の国星」などで有名な大島弓子先生も霊感があると聞いていましたが、その話も読むことができました。
構成
本書は5つのタイトルで構成されています。
・ゆうれい談…山岸先生自身と、アシスタントさんや漫画家仲間の方が体験した幽霊話
・読者からのゆうれい談…読者の方から寄せられた幽霊話
・蓮の糸…山岸先生自身やご家族で体験した幽霊話
・ゆうれいタクシー…山岸先生の実体験に基づくゆうれいタクシー体験とその考察
・タイムスリップ…山岸先生のお知り合いの実体験及び過去の資料などからタイムスリップについて考察
かなり多数の体験、しかも実すべて体験というところがすごいです。バラエティに富んでおり、参考になります。
感想
感想①マンガという媒体でしか描き得ない
この作品はマンガですが、あえてこのブログで紹介しようと思ったのは、この作品は文章のみでは到底描けなかったものであり、マンガという括りに入れるのが惜しいと思えるほどのものだと感じたからです。
というのも、幽霊というのは、やはり何かを「見た」という体験になります。
そもそも幽霊といったものは固定した形をしていないため、文章上で読者とイメージを共有するのは難しい。ですが絵にしてもらうことで、はっきりと筆者と読者のイメージがつながります。
これは山岸先生自身霊感があり、かつ筆力のある漫画家さんであったからこそできた技。奇跡的な作品だと思います。山岸先生の絵は非常にすっきりした線の絵ですので、それも雰囲気に合っています。
感想② 山岸先生の人間的かつ冷静な観察眼、考察力がすごい
霊体験をしたことのない私にとっては信じ難いほど、山岸先生の周りでは霊体験の話が多いです。
だからといって山岸先生自身がそれに慣れてしまっているわけではなく、その都度怖がり、驚いています。しかし、キャー、怖いで終わらないのが先生のすごいところで、「なぜ」自分のところにその霊が来たのか、「なぜ」その霊はそこに居たのか、何を伝えたかったのか…ということを冷静に考察されています。
幽霊ももとはといえば同じ人間。成仏せずにそこにいるということは、何かしらの理由があるはず、と、生きている人間と同じように扱ってらっしゃる。そういう優しい人だからこそ、霊側も何かを伝えたいと思って山岸先生の前に現れるのかも、と思いました(ご本人の体質もあるかとは思いますが…)。
感想③ 幽霊=怖い、ではない、全く新しい「ゆうれい談」
最初に書いたようにこの作品はすべて実体験です。ですので、内容は千差万別。怖いものもあれば、心温まる体験も。
私が特に印象に残ったのは、家族や仲間への愛情ゆえに会いに戻ってきたであろう霊たちのお話。特に山岸先生の愛猫の話は何度読んでも泣けます。体は失われても、愛する人たちへの想いが現世にとどまってしまう。そして、現世に留まらず、成仏して幸せになってほしいと願う遺族。これほど純粋な愛があるでしょうか。
この作品はただのオカルト本ではなく、普遍的な人間の愛についての作品であると思います。おすすめです。